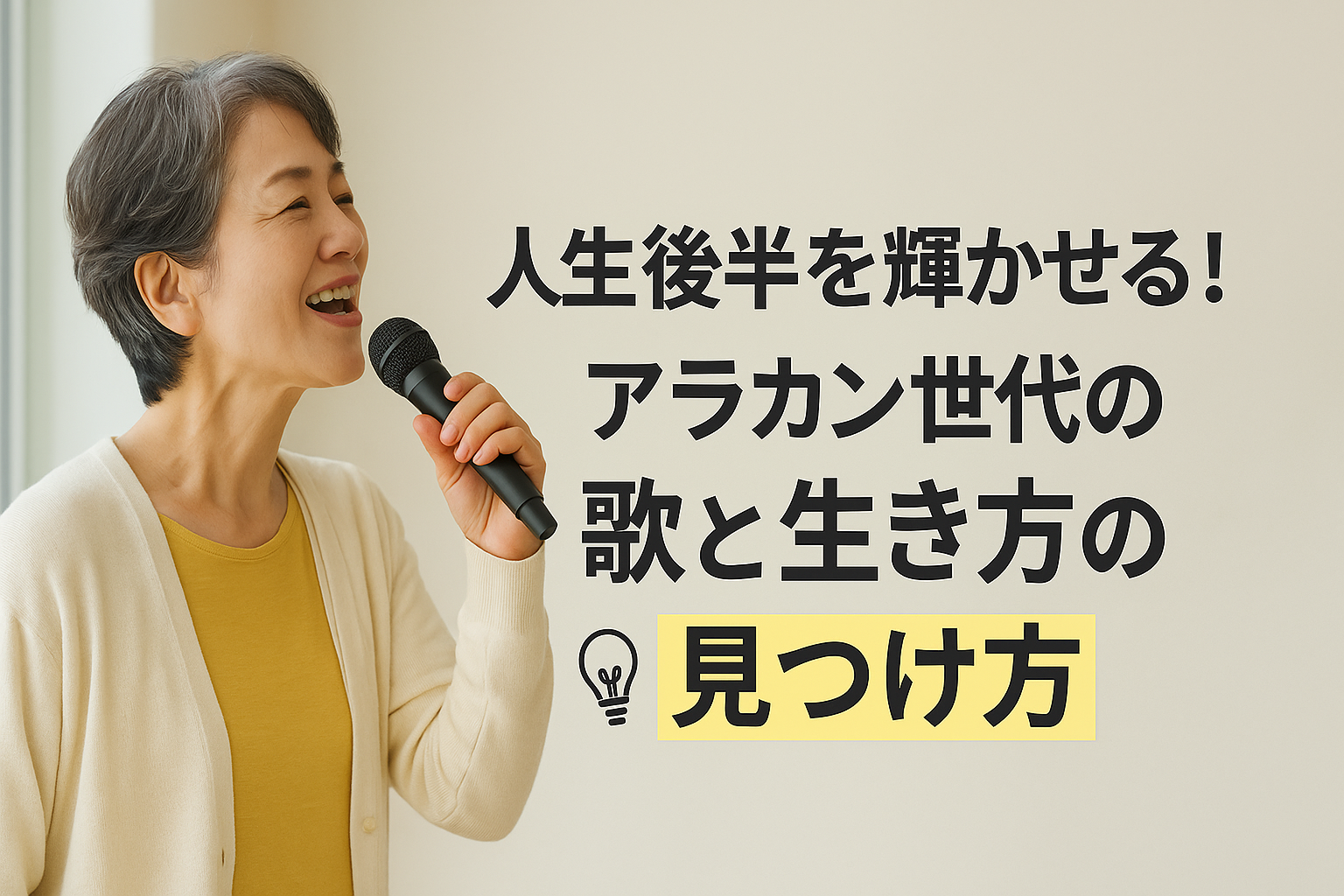私は小学生の頃から替え歌が大好きでした。
給食の時間や休み時間にオリジナルの替え歌を作っては、クラス中を笑わせていたんです。
当時はただの遊びでしたが、大人になった今、あの「替え歌作り」が実は作詞にとても役立つと実感しています。
実際、これまでにビーチボーイズの「KOKOMO」やディズニー映画『リロ&スティッチ』の「アロハ・エ・コモマイ」など、名曲を題材にして替え歌を作ってきました。そして、ウクレレの生徒さん達といろんなところで歌っています。
さらに替え歌が高じて、改変曲として「オー・シャンゼリゼ」を大阪バージョンにアレンジした「オー、ミドースジ」という曲もストリーミング配信発表しました。
これがまた、ウクレレの生徒たちや地元の人たちから「大阪らしくて面白い!」と好評をいただいています。
そんな経験から、今日は「替え歌がいかに作詞力を爆上げするか」というテーマでお話しします。
これから作詞を学びたい人、もっと表現を磨きたい人には、きっと新しいヒントになるはずです。
1. 替え歌は「遊び」ではなく最高の作詞トレーニング
「替え歌」と聞くと、バラエティ番組や飲み会の余興、友達を笑わせるネタ…そんなイメージを持つ人が多いかもしれません。でも実は、それだけで終わらせるにはもったいないほど、奥が深い世界なのです。
替え歌は、作詞スキルを高めるための最強トレーニングメソッドのひとつです。
特に歌詞に欠かせない「語感」「リズム感」「言葉選び」の3つを、一度に磨けるという点が大きな魅力です。
既に完成されたメロディに言葉をはめ込むという制約は、一見すると不自由に思えますが、実はこの「枠の中でどう表現するか」という課題こそが、表現力を飛躍的に伸ばしてくれます。
自由に書けるオリジナルの作詞とは違い、音数、リズム、メロディラインに合わせて言葉を選ぶ必要があるため、発想力、柔軟性、推敲力が徹底的に鍛えられるのです。
また、普段なら思いつかないようなフレーズを「どうにかこの音数に収めたい!」という欲求から無理やりひねり出すこともあります。この過程で、自分でも驚くような新しい表現や面白い言葉遊びが生まれる瞬間があります。
思い通りに言葉がメロディにぴったりはまり、スムーズに歌えたときの快感は、一度味わうとクセになるでしょう。
この「できた!」という感覚が、自信と楽しさにつながり、さらに作詞を続けるモチベーションになります。
遊び感覚で始められるのに、気づけば本格的な作詞トレーニングになっている――それが替え歌の最大の魅力です。
2. 替え歌で鍛えられる3つの力
① 語感センス
歌詞の「語感」とは、耳に届いたときの響きの心地よさや、口に出したときの滑らかさのことを指します。
ヒット曲の多くは、聴き手が思わず口ずさみたくなる「気持ちいい」言葉の選び方がされています。
替え歌は、既存のメロディに言葉を乗せる必要があるため、自然と「この言葉は硬いかな?」「もっと柔らかい言葉の方がメロディに合うかも」といった感覚が磨かれます。
繰り返し作るうちに、自然と耳に心地よい音の組み合わせや、歌いやすい言葉の選択ができるようになります。
つまり、替え歌は遊びながら語感センスを鍛える最高のトレーニングです。
② リズム感
歌詞が詰まりすぎると歌いにくく、逆にスカスカだと間延びしてしまい、聴き手に違和感を与えます。
替え歌では、元のメロディにピッタリ合わせる必要があるため、言葉の長さ(音数)とリズムのバランスを常に考える癖がつきます。
「このフレーズは1音多いな」「ここはもう少し詰めた言い回しにしよう」と、自然に調整する力が身につき、これがそのまま作詞のリズム感向上につながります。
また、替え歌では実際に歌いながらリズムを確認するので、机上の理論ではなく「体感的なリズム感」を育めるのが大きな魅力です。
プロの作詞家でも、最終チェックでは必ず声に出してリズムを確認するというほど、リズム感は歌詞の命ともいえる要素です。
③ ストーリーテリング力
歌詞は単なる言葉の羅列ではなく、一曲を通して「小さな物語」を描くものです。
替え歌では「笑わせたい」「共感させたい」「驚かせたい」といった目的に合わせて、短い時間でストーリーを完結させる力が求められます。
たとえば、「仕事の愚痴ソング」にするなら、最初に月曜の憂うつを描き、途中で上司への不満を入れ、最後に「金曜日が待ち遠しい!」とオチをつける、といったように、聴き手に物語の流れを感じてもらう構成が必要です。
替え歌を繰り返すことで、「どんな順序で気持ちを動かすか」「どこで笑わせるか」「どう締めるか」といったストーリーテリングのスキルが鍛えられます。
この力があれば、オリジナルの歌詞を書く際にも自然と「物語性」が加わり、聴き手を引き込む作品が作れるようになります。
✅ 替え歌を続けることで、この3つの力は相乗効果で伸びていきます。
まずは楽しむことを一番に、少しずつ感覚を磨いていきましょう!

3. 替え歌練習の具体ステップとコツ
ステップ1:好きな曲を選ぶ
まずは「自分が何度も聴いて知っている曲」を選ぶことが大切です。
好きなアーティストの代表曲、子どもの頃に歌った童謡、よくカラオケで歌う曲など、メロディやリズムが自然と頭に入っている曲だと、言葉をはめやすく作業がスムーズに進みます。
特にテンポがゆっくりめで、言葉数が多すぎない曲がおすすめです。
ステップ2:テーマを決める
歌詞を作り始める前に「何を伝える替え歌にするか」をしっかり決めましょう。
テーマが決まらないままだと、途中で内容がブレてしまい、まとまりのない歌詞になります。
例:
- 仕事の愚痴ソング(例:「月曜日の憂うつ」テーマ)
- 推し活あるあるソング(例:「推しに会えた日の高揚感」テーマ)
- 自分の町の紹介ソング(例:「地元の商店街や名物を紹介」テーマ)
テーマを決めると、自然と使いたい言葉が浮かびやすくなります。
ステップ3:キーワードを書き出す
テーマが決まったら、それに関連するキーワードを10〜20個ほどメモします。
例えば「仕事の愚痴ソング」なら、「残業」「満員電車」「上司」「週末」「休みたい」など…。
このキーワードが、あとで歌詞を組み立てる土台になります。
キーワードを書き出すだけでも、曲に入れたい要素が整理され、歌詞の方向性がぐっと定まりやすくなります。
ステップ4:ワンコーラスだけ完成させる
いきなりフルコーラスを書こうとするとハードルが高く感じるので、まずはAメロからサビまでの「ワンコーラス」だけでOKです。
短い部分だけでも完成させると、達成感があり自信がつきます。
一部分でも形にする経験を積むことが、継続するコツでもあります。
ステップ5:声に出して歌う
完成したら必ず実際に歌ってみましょう!
画面や紙で見ているだけでは気づかない、リズムのズレや言いにくいフレーズが見つかります。
声に出して確認すると「ここは文字数が多いな」「この言葉は発音しにくいな」といった改善点がわかり、より歌いやすい歌詞にブラッシュアップできます。
コツ:完成度を求めすぎない
最初から完璧を目指さなくて大丈夫です。
「うまくいかなくてもOK」「とりあえず作ってみる」くらいの気持ちで、楽しむことを一番に考えましょう。
とにかく数をこなすうちに、自然とリズム感や言葉選びのセンスが磨かれていきます。
✅ このステップを繰り返していくうちに、自然とオリジナルの歌詞を作るための基礎力が身につきますよ!
4.私の替え歌披露します。ビーチボーイズ「KOKOMO」
ここで、私自身が実際に作った替え歌を披露します。
題材にしたのは、ビーチボーイズの名曲「KOKOMO」。映画『カクテル』の主題歌としても知られていて、まさに「常夏」のイメージをまとった楽曲です。
私はこの曲が大好きで、「いつかウクレレで気持ちよく歌いたい!」と思っていました。
ただ、原曲のままだと英語で歌うハードルが高い…
そこで、常夏な雰囲気を活かしつつ、ウクレレで歌っても楽しくなるように、日本語の替え歌を作ったのです。
🎤 私の歌詞はこうなりました。
英語の詞を日本語に訳したのではありません。言葉がメロディに合うように、まったく新しいアプローチで書いていきました。
YouTubeで曲を流しながら歌詞を追っかけてみてください。
アルバ ジャマイカ 君を連れて
バミューダ バハマ あの場所まで
キーラーゴ モンティーゴ もう気分は
ジャマイカ
目を閉じれば ここは楽園ココモ
すべてを脱ぎすてて 自分になれる
砂にまみれ 夏のカクテル飲めば
乾いたリズム 恋に落ちてくようだね
乾杯ココモ
アルバ ジャマイカ 君を連れて
バミューダ バハマ あの場所まで
キーラーゴ モンティーゴ
気持ちがイイよね ココモ
お持ち帰ればいいさ みんな待ってる
ココモ 最高
海に出れば 波と風との匂い
シナリオ気にしてちゃ 恋はできない
午後の陽射し やがて月夜に変わる
夢見る 君の視線で 踊り明かそう
ココモ 最高
このように、既存のメロディに日本語歌詞を当てはめると、ただカバーするだけではなく、自分だけの表現になります。すなわち自分の作品になる。
この曲は夏の歌なので、ウクレレという楽器との相性も抜群、より自然体で楽しめるような気がしますが、いかがですか?
これまで説明してきたように、替え歌は「遊び」ではなく、作詞スキルを磨くための最高の練習法です。
私自身、この替え歌を作る過程で語感、リズム、ストーリー性の大切さを改めて感じました。
✅ 替え歌を楽しむことは、作詞家としての一歩目にもなります。
あなたもぜひ、自分の好きな曲で挑戦してみてください!
5. 替え歌から一歩進んで「自分の曲」を作る方法
替え歌で鍛えたスキルは、そのままオリジナル曲制作に活かせます。
- 替え歌で学んだ語感・リズム・テーマ設定は、オリジナル歌詞の基礎になる
- 「歌詞は書けるけど曲が作れない」という人も、替え歌経験があればメロディづくりのヒントを得やすい
上の「KOKOMO」日本語バージョンは、
この詞だけをとりだせば、完全な私のオリジナルになるわけです。
KOKOMOを違う言葉に、例えば「ハバナ」とか「UMEDA」とか(笑)に変えて自分の曲にしてしまいましょう。
そして、もう1歩進める方は、
⭐️替え歌を書いて、それに新しい曲をつけると、
完璧な1曲、オリジナルソングの完成になります。
実際に私も1曲作り、配信リリースしています。このやり方もいずれ別に記事でお伝えしますね。
また、替え歌だけで、配信販売や著作権登録にもチャレンジできます。
「オーシャンゼリぜ」を改変して「オー・ミドースジ」を作ったのもこのやり方でした。
もし真剣にこの方法で、正規の方法で世界に発表して印税まで手に入れたいと思う方は以下の記事をぜひ読んでください。「オー・ミド–スジ」が承認されるまでのストーリーが楽しめますよ。
6. まとめ:あなたの遊び心が未来のヒットを生む
替え歌は、ただの「ふざけた遊び」ではありません。
実は、プロの作詞家やシンガーソングライターも取り入れている、れっきとした本格的な作詞トレーニングです。
完成されたメロディに言葉を当てはめるこの作業は、一見すると制約だらけのように感じるかもしれません。
しかし、その「縛り」の中で工夫を重ね、思わず口ずさみたくなる言葉を紡ぎ出す過程こそが、あなたの表現力や語感センスを爆発的に伸ばす最短ルートなのです。

今、思いついた言葉が、何気なく書いたフレーズが、未来の自分にとってかけがえのない武器になります。
替え歌を通して培ったスキルは、やがてオリジナル曲を書くときにも必ず活きてきます。
そして何より、あなたが作った歌詞が、誰かの心に届き、笑顔や涙を生む――そんな未来が本当に訪れるかもしれません。
「自分にそんなことできるのかな?」
大丈夫です。まずは1行、1フレーズ、ワンコーラスからでいいんです。
遊び心で気軽に始めてみてください。楽しんで続けるうちに、気がつけばあなたの中に「作詞家」としての新しい可能性が芽生えているはずです。
💬 感想や「作ってみたよ!」という報告も大歓迎です!
ぜひコメント欄でシェアして、一緒に楽しみましょう!
あなたの挑戦を、心から応援しています。